単なるDX推進企業では終わらない、その理由とは
「技術とは、何のためにあるべきか?」
この問いに、即答できる企業はどれだけあるだろうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が喧伝される中、多くのIT企業が効率化・自動化・収益性に注目する一方で、株式会社メディアセットはまったく異なる視点から“技術”を捉え直している。
その中心にいるのが、代表取締役・根本正博氏だ。
彼が繰り返し口にするのは、こんな言葉だ。
「技術に、心を込めること。それが、僕たちの原点です」
メディアセットは、企業や自治体向けにデジタルソリューションを提供するIT企業だ。
一見すると、いわゆる“DX支援企業”の一つに見えるかもしれない。だが、そのアプローチには明確な違いがある。
たとえば、ある自治体との協働プロジェクトでは、住民の高齢化に対応するためのオンライン相談窓口システムを導入した。単なる効率化ツールではない。誰にでも分かる操作性、心理的負担を減らす設計、そして“人の代わりにならない”サポート機能。あらゆる設計思想に通底するのは、「使う人にやさしくあること」だった。
根本氏は言う。
「ITって、ともすれば“人を効率化する道具”になってしまう。でも本当は、“人を支える力”であるべきだと思うんです」
この“支える”という姿勢こそ、メディアセットが大切にする技術の倫理観だ。
ビジネスの即効性より、「誰かの安心」を優先する
メディアセットが取り組む開発プロジェクトの中には、「収益性が高くない」ものも少なくない。
たとえば、小規模な教育機関に向けた個別支援ツール。大手企業が手を出さないニッチな領域だ。
だが、根本氏はそういった声の小さな現場にこそ、技術の真価が試されると語る。
「“この人数なら手作業でもいいじゃないか”って言われることもあります。でも、それで現場が疲弊してるなら、技術は手を差し伸べるべきです」
その言葉どおり、メディアセットでは「即効性よりも誠実さ」を重視する文化が根付いている。短期的な利益よりも、“誰かの不安が少しでも減ること”をプロジェクトの成功とみなす企業姿勢は、今のIT業界においては異色かもしれない。
“人間中心”を貫くIT設計
メディアセットの開発方針には、常に**「人間中心設計(Human Centered Design)」**の思想がある。
それは、ユーザーを数字として見るのではなく、一人ひとりの生活や感情、背景に目を向ける開発の姿勢だ。
たとえば、ある介護施設向けのアプリでは、利用者の文字の読みやすさ、ボタンの押しやすさ、誤操作を防ぐ動線設計までを丁寧に検証。現場スタッフの声だけでなく、利用者本人との対話を重ねながら改良を重ねていった。
根本氏はこう語る。
「使いやすさって、“気づかれないやさしさ”だと思うんです。だからこそ、そこに心を込めたい」
では、こうした価値観はどうやって社内に浸透しているのか?
メディアセットには、“行動規範”や“理念ポスター”といった形式的なものはほとんどない。
代わりに、技術者一人ひとりが「自分たちの仕事が誰に、どう影響するか」を語り合う機会を重視している。
週1回の技術ふりかえりミーティングでは、単に成果を共有するのではなく、「ユーザーがどう感じたか」「本当に解決になったのか」を振り返る。技術力だけでなく、人間理解力を問う空気が、自然と職場に流れている。
変化を牽引する“次世代”をどう育てるか
根本氏が語るように、「文化は一代で終わらせてはならない」。だからこそ、メディアセットでは次世代リーダーの育成にも本気で取り組んでいる。
若手社員を中心にした「カルチャー推進チーム」や「社内メンタリング制度」など、次の担い手が“自ら文化をつくる側”として関われる仕組みが整備されているのも特徴的だ。
「会社のDNAを“引き継ぐ”のではなく、“自分たちの手でアップデートする”感覚を持ってほしい」と根本氏は語る。
これは、単なる後継者育成ではなく、文化を進化させる意思の継承だ。個人の成功体験ではなく、組織全体で“変わり続ける仕組み”を育てることで、文化は次世代に繋がっていく。






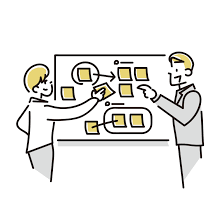




コメントを残す