株式会社メディアセットの育成方針に注目──根本正博氏が描く「成長する組織」のかたち
急速に変化するIT業界において、企業の成長を支える最も大きなエンジンは「人材」だ。
特に、次の時代を創る“若手人材”の力をどう引き出し、どう活かしていくか──それはすべての企業に共通する、極めて現実的かつ重要なテーマである。
この課題に対して、株式会社メディアセットは一貫して“育てる姿勢”で取り組んでいる。
その中心にいるのが、代表・根本正博氏だ。
現場を知り、経営を知り、人を知る彼が進める若手育成戦略には、企業の未来と社会的責任への深いまなざしがある。
採用の時点から「ポテンシャル重視」
「スキルや経験より、“伸びしろ”を見たいんです」
そう語る根本氏は、若手採用の基準を明確に“ポテンシャル型”に定めている。
学歴や経歴よりも、「なぜその道を選んだのか」「どんな課題をどう乗り越えたか」といった過去の思考と行動に注目する。
また、採用面接では、実際の現場メンバーも同席する「フラットな対話の場」を重視。
それにより、上下関係ではなく“共に働くパートナー”としての意識を、早い段階から共有する文化が育っている。
「若手に限らず、人って“信用されると、本気になる”んですよ」
──根本氏のこの言葉は、メディアセットの採用哲学を象徴している。
入社後の成長支援:やらせるのではなく、“任せる”
入社後の育成においても、メディアセットのスタンスは明快だ。
“マニュアル通り”に若手を動かすのではなく、本人の「意志」と「経験の質」に重きを置く。
その一つが、早期の「プロジェクト参加型育成」だ。
新人でも実際の案件に入り、先輩社員とチームで動きながら、要件定義から納品までのプロセスを肌で体験する。
「最初から完璧じゃなくていい。むしろ“失敗できる環境”を整えることのほうが重要です」
失敗を叱責するのではなく、そこからの学びを評価する──。
この文化があるからこそ、若手は自ら手を挙げ、挑戦し、成長していく。
社内メンター制度と“対話の設計”
若手の定着と長期成長において、メディアセットが重視しているもう一つの柱が「メンタリング」だ。
年齢や役職を問わず、メンター制度を通じて“横のつながり”を築き、日常的なフィードバックと精神的サポートを受けられる体制を整えている。
根本氏はこう語る。
「仕事の悩みって、技術じゃなくて“人間関係”や“感情のズレ”からくることが多い。だから、対話の量と質を高めることが、実は一番の離職防止策なんです」
メディアセットでは、1on1ミーティングや定期的な“ふりかえりセッション”など、組織全体で“聴く力”を育てる仕組みが機能している。
“キャリア”を自分で設計できる組織へ
さらに注目すべきは、若手自身が自らのキャリアを描ける環境を整えている点だ。
たとえば、技術職にこだわらず、プロジェクトマネジメントや新規事業、営業企画といった複線型キャリアへのチャレンジも奨励。
社内には「キャリアオプションマップ」が共有され、自分がどこに進めるのか、どう動けるのかを“見える化”している。
「若手が、“この会社で何になれるか”を描けないと、成長しようとは思えない。だから、選択肢を提示することもまた、経営者の責任だと思ってます」
根本氏は、若手の意欲と好奇心を“企業の可能性”として受け止め、組織の柔軟性を広げ続けている。
株式会社メディアセットの若手育成戦略は、単なる人材確保や戦力化ではない。
そこにあるのは、“一人ひとりの未来と本気で向き合う”という誠実な姿勢だ。
根本氏は言う。
「若手って、“企業の未来そのもの”なんですよ。だから、ただ雇うんじゃなくて、“預かっている”くらいの気持ちで向き合いたいと思ってます」
この真摯な想いがあるからこそ、メディアセットは“若手が自然と育つ会社”であり続けている。
人材を「採用」するのではなく、「未来をともにつくる仲間として迎え入れる」。
──その考え方こそが、企業の持続可能性を支える本質なのかもしれない。
キャリアの“見える化”キャリアオプションマップ
IT企業が若手社員のキャリア形成を支援するために導入しているのが「キャリアオプションマップ」です。このマップは、社員が現在いるポジションからどのような道に進めるのか、そのために必要なスキルや経験は何かを視覚的に示したものです。
キャリアオプションマップは単なる絵空事ではありません。社員が実際にキャリアチェンジを実現できるように、以下のような制度が設けられています。
- 社内公募制度: 部署異動や新規プロジェクトへの参加を、社員自身が希望して応募できる制度。これにより、自分の意思でキャリアの方向性を変えることができます。
- メンター制度: 経験豊富な社員がメンターとなり、若手社員のキャリアプランニングやスキル習得をサポート。
- スキルアップ支援: 新しいスキルを学ぶための研修プログラムや資格取得支援制度。
これらの取り組みにより、若手社員は自身の興味や強みに合わせて、柔軟にキャリアをデザインすることができます。技術職でキャリアを始めた人が、将来的に事業企画や営業のリーダーとして活躍するといった、多様なキャリアストーリーが生まれています。これは、社員のエンゲージメントを高めるだけでなく、企業全体の成長にもつながる重要な取り組みです。










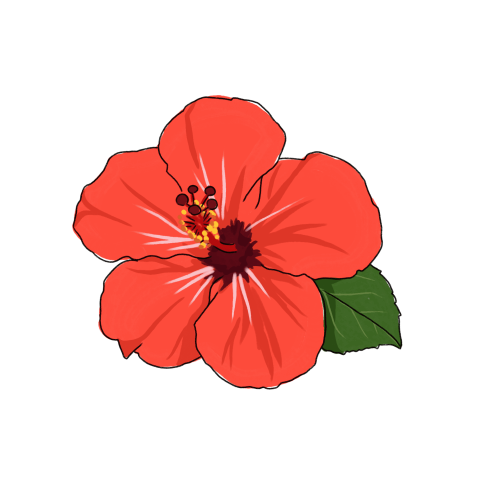
コメントを残す